2024年07月30日
あいさつをしない子どもたち

いや別に奈良のことを悪く言うつもりはないのだけれど、こっちに来て最初に一番違和感を感じたのは、あいさつを、みんなあまりしないことだ。
ま、どちらかというとこちらが日本の平均値に近く、奄美がよくあいさつをする地域だということなのかも知れない。
奄美の時も、小学校の朝の旗振り当番で、今日はあいさつしない子多いなー、なんて思ったことがあったが、まったくその比ではない。
引っ越し当初、通学班の子たちが玄関まで迎えに来てくれていたのだが、おはようって言っても誰もあいさつを返してくれないし、目も合わせてくれない。
ああ、6年生の班長の女の子だけは返してくれたっけ。
でも、そんな感じだった。
しばらくは、まだ面識が浅いから恥ずかしいのかな、と思っていたが、そういうことでもないらしい。
それでその理由は、連れ合いが出席した学校の保護者会かなにかの時に出た話で、ようやく明らかになった。
何年か前に、事件があったそうだ。
いつも通学路でニコニコ愛想よく、子どもたちにあいさつしてくれるおじさんが、子どもを誘拐し、殺めてしまったという事件が。
それ以来、この辺りの子どもたちは、あいさつしてくる大人を警戒するよう教えられているのだそうだ。
だからか。
キャンプ場の朝食後の洗い場で、先に食器を洗っていた親子にあいさつしたら、警戒心満載の目で睨み返されたのは。
街中ならまだしも、キャンプ場でそんな仕打ちに合うとは思わずビックリしたが、そういうことだったのか。
でも、どうなんだろう。
その考え方も一理あるかも知れないが、だからって警戒ばかりしてあいさつを返さないって、本末転倒な気がする。
あいさつというコミュニケーションの第一歩から断絶するのではなく、相手を見極める目や知恵、警戒すべきかどうかを判断する力を身につけさせてあげることが大切なのではないだろうか。
確かに難しいかも知れないし、リスクを伴うかも知れないが、断絶からは何も生まれないし、目や知恵も身につかない。
少なくともさ、友だちのお父さんなんだから、あいさつ返して欲しいなー、と思う訳ですよ。
いろんな人がいるから警戒することはもちろん必要。
でもまあ、世知辛い世の中だ。
Posted by 井田陽平 at
20:59
│Comments(0)
2024年07月29日
自警団

ひょんなきっかけで、奈良に来て自警団に入ることになった。
自警団とは、奄美で言う青年団や壮年団みたいなもので、地域の夜警や防災、イベントの運営などを任務とする有志の団体だ。
郷に入っては郷に従え。
千葉から奄美に移住した時も、できるだけ地域のイベントには参加しようと思っていたし、保育園や小学校の役員なんかも積極的に引き受けてきた。
保育園の保護者会長は確か3回、小学校の役員も毎年どこかの学年の学年長を務めさせてもらった。
奄美に移住した時は、一番上の子が2歳半と小さかったこともあり、地域のイベントや子育てサークルなんかにも参加する機会が多かった。
そのおかげで、自分たち的にはとてもすんなりと、地域になじめたと思っている。
男の子2人は、朝仁集落の豊年相撲で、化粧まわしを付けて土俵入りさせてもらったのも、最高の思い出のひとつだ。
という訳で、奈良の自警団へのお誘いに乗っかってみた。
朝仁青年団もそうだったが、こちらの自警団もとても居心地がいい。
無償で地域のために活動しようと集まっている人たちなので、当然と言えば当然なのだが、みんないい人ばかりだ。
先日の土曜日は、盆踊り大会があった。
前々から協賛金集めや買い出しなどの準備を始め、当日はもちろん、翌日の後片づけまで(自分は協力できない日も多かったが)、ひと通り働かせてもらった。
今年はかき氷の担当だったので、ひらすら氷を削った。
おかげで腕が軽い腱鞘炎になったようで、翌日の朝まで少し痛かったが、これもまたいい思い出だ。
こういう話、奄美人にとっては超あるあるですよね。
いろんな場所で暮らしてきた私が言うのだから間違いない。
奄美人は、イベントのプロフェッショナルだ。
あんなにイベントが多くて、かつ、楽しみ方を知っている地域も珍しい。
奄美はこれから奄美祭りだが、こちらの次は秋祭りだ。
これがまためちゃんこハードなイベントなので、その時またここで報告しよう。
それまでは月1回の夜警と、放水訓練にしっかり参加してと。
自警団。
何だか上手くまとまらないが、何だか意義のあることが出来ているような気がして、心地よく活動している。
Posted by 井田陽平 at
20:41
│Comments(0)
2024年07月26日
ブルジョアな習い事

奄美から奈良へ移住したのは、長女が中学に上がるタイミングだった。
奄美で桜と言えば緋寒桜だが、奈良はもちろんソメイヨシノ。
桜の花びらがひらひら舞う中での、絵に描いたような晴れやかな入学式。
この咲き誇り舞うソメイヨシノの美しさは、雪と並んで、奄美の子たちに見せてあげたいものの筆頭に来る事象だ。
密かに興味を持っていたのは、場所も人間関係も全く新しいこの環境で、娘が何の部活を選ぶかだ。
小学生までの習い事は、保育園から続けている新体操と、週に1回のティダスポーツの体操。
ほぼ毎日、学校と三儀山を往復して過ごしてきた。
なのでまあたぶん、運動系の部活には入るんだろうなー、と思っていた娘が選んだのは、吹奏楽部。
新しい友だちや、体験入部してみての感じなど、きっといろいろあったのだろう。
中3になった今になってみれば、彼女に最も合う部活だったと思うけれど、当初は少し意外な選択に思えた。
ただ、新体操か体操は続けたかったらしく、近隣の習い事を探したのだが、ピンとくるところが見つからない。
で、最終的に行き着いたのが、なんとクラシックバレエ。
これまた予想だにしなかった展開が待っていたのであった。
今年は受験生で、この夏から少し週の回数を減らすようだが、ここまで週5回。
クラシックバレエを始めるには決して早くない学年からのスタートだったにもかかわらず、よく頑張っている。
大きな発表会でもソロパートを躍らせてもらったし、本人も踊るのは好きみたいだし、習わせてよかったと思っている。
でも、改めて客観的に考えると、楽器とクラシックバレエって、どこぞのブルジョア階級だよって習い事だ。
まあ、そんなことはどうでも良いのだけれど。
そんな娘も、来年は高校生。泣いても笑っても、だ。
合わせて長男も中学に上がるので、この二人が部活なり習い事なり、どんな選択をするのか今から楽しみだ。
その前に、おおきな心配事が待ち構えてはいるのだけれど。
Posted by 井田陽平 at
21:08
│Comments(0)
2024年07月25日
ライナスの毛布

我が家はたぶん、すごくモノが多い家だと思う。
整理整頓云々以前の問題として、家の中にモノが溢れている。
子どもが一人増えるごとにモノも当然増えるわけだが、奄美からの引っ越しの時は、この狭い家によくもまあ、というほどモノが詰め込まれていたことに嘆息した。
だいぶいろいろ捨ててきたのだが、引っ越し当日にもトラックに詰め込めない荷物が大量にあり、友人やお隣さんに処理を押し付けるという狼藉を働いてしまった。
特にお隣のご夫婦、その節は大変ご迷惑をおかけしました(>_<)
そして今、特に溢れているのは洋服と本。
こちら(奈良)の学校は、小中学校ともに私服なので、必然的に洋服は増える。
中3長女の部屋などは、毎日フリーマーケット状態だ。
本に関しては、極力買わないようにしている、が。
引っ越しの時に大半は古本屋に売り、厳選された本のみが並んでいたはずの本棚に、少しずつ新しい本が加わっている。
プラス、基本的には図書館で借りてくるので、その本が収納しきれずにいつも溢れている状態だ。
それと何とかして欲しいのが、子どもたちのおもちゃ、と言うかガラクタ類。
ただ、こちらにはガラクタにしか見えないモノでも、ライナスの毛布ということがある。
ライナスの毛布とは、スヌーピーに登場するライナス君がいつも引きずっているあの毛布のことで、人がモノなどに執着している状態を指し、心理学でもよくつかわれる用語なのだとか。
多くは、幼児が何かに執着することで安心感を得る状態を指すが、成長したり大人になったりしても、ライナスの毛布が手放せないというケースもあるそうだ。
それで、例えば大事なぬいぐるみを捨てられてしまったことがトラウマになったとか、大事なカードを燃やされてしまったのでモノを隠すクセがついたとか、そんな話も聞く。
それは困る。だとすると、許可なしにおいそれとは捨てられない。
とは言え何とかしなければ。
ライナスの毛布と断捨離のバランスが、今日も我が家の課題である。
Posted by 井田陽平 at
11:49
│Comments(0)
2024年07月24日
読書の文化

奈良の子は、読書量が少ない。
もちろん個人差はあるだろうが、体感として少ないなと思うし、後述するが、そういうエビデンスもあるようだ。
奄美の小学校では、図書室の貸し出しトップをいつも獲得していたウチの子たちも、ほとんど学校から本を借りてこない。
というか先生がいないため、そもそも図書室がめったに開かないらしいのだ。
これはいけない。
ある調査によれば、小学生の読書率トップ3は、岩手県、鹿児島県、山形県。ワースト3が、沖縄県、大阪府、奈良県。
やっぱりね、という感じだ。
中学生になると全体の読書率が下がり、トップと最下位の差が開き、二極化が進む。
相関ランキングでいくと、人口集中度と負の相関(読書率が高いところは低い)、農業就業人口と正の相関(読書率が高いところは高い)がある。
平たく言えば、地方で読書率が高く、都市部で低いということだ。
さらに、子どもの生活習慣との相関でいうと、正の相関にあるのが、早寝早起き率、校則尊守率、朝食摂取率。
負の相関にあるのが、長時間ネット利用率、携帯電話スマートフォン所有率。
読書が良くてスマホはダメ、などと時代錯誤なことを言うつもりは、サラサラない。
だけどねえ、うーん、どうなんでしょうねえ、読書のメリットは大きいと思うけどなあ。
私は読書がわりと好きなので、これからも読み続けると思う。
そんな姿を見てか、自分の子どもたちは本好きに育ってくれたようだ。
「この本、面白かったよ^.^」と教えあったりするのは、とても楽しい。
奈良のことまで何とかしようとは思わないが、我が家の読書文化は受け継がれていきそうな予感がする。
とりあえずは、それでいいのかな。
Posted by 井田陽平 at
12:05
│Comments(0)
2024年07月23日
ビブリオバトらない

ビブリオバトルをご存じだろうか。
自分の好きな本を時間内にプレゼンテーションして、聴衆に読みたいと思わせた方が勝ちという書評プレゼンバトルだ。
京都大学で考案され、今では全国、各カテゴリーで大会が催されている。
我らが大島高校でも開催されているようで、ブログ記事を興味深く読ませていただいた。
私が所属しているあるコミュニティーでも、ビブリオバトルが開催されたことがある。
プレゼンはするが勝敗を決めないというルールなので、名付けて“ビブリオバトらない”。
こういうイベントは大好きなので、参加しない手はない。
さて何を選ぼうか。
とりあえずビブリオバトルをYouTubeってみると、何らかの授賞式のプレゼンターに、辻村深月が登場した。
大ファンだ。どの作品を読んでも面白い。
特に女子の妬み嫉みみたいなものを書かせたら、天下一品だと思う。
映画化もされた代表作『ツナグ』の一話、アラシとミソノの物語なんか、もう鳥肌ものだ。
で、結局選んだのは『ツナグ』ではなくて『鏡の孤城』。
辻村深月の最高傑作との呼び声も高いが、確かにそれに値する名作だ。
こんなところでネタばらしするよりも、ぜひご一読いただきたい。
こちらもアニメで映画化されているので、読書の苦手な方は映画を。優里の主題歌に泣かされる。
ということで、ビブリオバトルは面白いので、夏休みのイベントとして、ぜひ家族でバトらず開催しようと思っている。
本は漫画でももちろんOK。
かく言う私も、『北斗の拳』と『ベルサイユのばら』の魅力を、ある場所でプレゼンしてきたばかりだ。ビブリオバトルではなかったけれど。
さて、家族の“ビブリオバトらない”にはどんな本を選ぼうか。
https://amzn.to/3Ly8JXg
https://amzn.to/4d90aOz
Posted by 井田陽平 at
11:05
│Comments(0)
2024年07月22日
もんちゃんという男
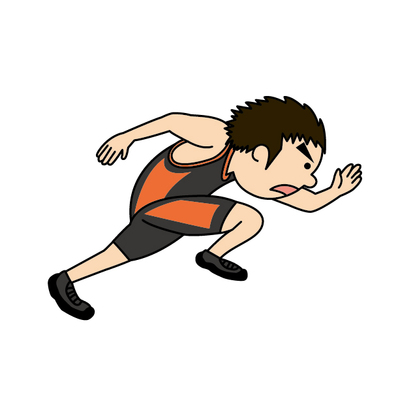
息子2人は、小学5年生と6年生になった。
奄美では週に1回、本山先生に陸上を習っていたが、こっち(奈良)に来てからも陸上を続けている。
いま通っているクラブは結構な大所帯で、コーチが何人もいるのだが、呼び方は「〇〇コーチ」だったり「〇〇ちゃん」というニックネームだったり、いろいろだ。
その中に、子どもから保護者にまで「もんちゃん」と呼ばれているコーチがいる。
まだ20代の若者なのだが、実に気さくな人柄で話しやすく、めちゃくちゃ面倒見もいい。
ゆえに子どもたちから絶大な人気を誇り、保護者からのウケも抜群だ。
先日、小学生から社会人までが参加するとある大会があって、もんちゃんも選手として100m走に出場した。
会場は、いつも練習で使っているスタジアム。
出走前の選手紹介に、スタンドの子どもたちからホームの大声援が飛ぶ。
照れくさそうに右手を上げるもんちゃん。
さあいよいよレース開始、ゴール後に足を抱えて倒れこむもんちゃん。
肉離れを起こしたらしい。
もんちゃんの一大事に、応援席がざわめく。
心配でいてもたってもいられなくなった子どもたちは顔を見合わせ、勝手知ったるホームスタジアムを走り、もんちゃんの元へ向かう。
数十分後、車いすに乗ったもんちゃんが、はにかみながら子どもたちに囲まれて応援席に帰ってきた。
保護者からも拍手と、ねぎらいの声がかけられる。
観戦に来た卒業生の女の子から「こんな日もあるさ。くじけず頑張りたまえ^-^」と、肩を叩かれミニコントをしている。
いい風景だな、羨ましいなと思った。
さっきは照れくさそうに手を上げたもんちゃんだったが、やはり声援は相当嬉しかったに違いない。
いいとこ見せたかったに違いない。
だから肉離れするまで頑張っちゃったんだろう。
そんなもんちゃんだから、人気がある。
それが、もんちゃんという男だ。
Posted by 井田陽平 at
11:58
│Comments(0)
