2024年08月21日
あまみエフエム ディ!ウェイヴ!

えらいもんで、昨今はインターネット放送でラジオが聴けるようになった。
おかげさまで我が家はみんな、奄美時代よりもさらに、あまみエフエムのヘビーリスナーになっている。
なかでも連れ合いはスーパーヘビー級。
イベント情報やお得情報など、現役奄美人と同等かそれ以上に、島の情報に詳しいはずだ。
子どもたちも子どもたちで、今日は陽子姉だねーとか、おー丸田さんだ!とか言って楽しんでいるようで、家の中の雰囲気は奄美時代と何ら変わらない。
保育園の時に「島の宝奄美っ子」のコーナーで、陽子姉ちゃんと蘭姉ちゃんにインタビューしてもらったと、今でも楽しそうに話す。
かく言う私も大ファンで、呼ばれたり自分で売り込んだりして、何度も出演させていただいたことがある。
あまみエフエムとの初めての思い出は、奄美に移住して間もないころに遡る。
まだオープンほやほやのAiAiひろばで、利き黒糖焼酎のイベントが開催されており、当時2歳と0歳の子どもを連れて通りかかったのが事の始まり。
チャレンジして行きませんかと声をかけていただき、夫婦で壇上に上がり、見事チャレンジ成功!
(ちょっとヒントをもらったけれど)
あの時、満面の笑みでマイクを向けて、「どうですかっ!?」と、これ以上ない大雑把な質問を投げかけてきたのが誰あろう、あの渡陽子さんだった。
今ではあまみエフエムの顔として全面前面でご活躍だが、元々は裏方の役割をされていたそうで、その時は表方の役割を務めるようになって間もない頃であったと、後々になって知った。
今は昔。どうりで質問が雑かったわけだ。
インターネット放送からは、流暢に質問するご様子を拝聴しているが、オレはデビュー当時の渡陽子にインタビューされたことあるぜって、ひとつの自慢話にしている。
っていう話を、ある機会にご本人にお話ししたところ、なんとその時のことを覚えていてくれたのだ。
これは嬉しかった。
私のことに限らず、放送を聴いていれば分かるが、彼女はいろんなことをホントによく覚えている。
それこそ「はげ~、感心~(#^.^#)」じゃや。
そんなわけでこれからも、あまみエフエムを聴き続けようと思った次第である。
できればまた出演もしてみたい。
あまみエフエムよ、永久に不滅であれ!!
Posted by 井田陽平 at
11:54
│Comments(1)
2024年08月19日
一日一話

夏の甲子園もベスト8が出そろい、夏休みもいよいよ終盤を迎えた。
間際になって宿題に追われるのは、どの家庭でも夏の風物詩だと思っているが、わが家も例に漏れないことが多い。
一応それなりに声かけはしているので、まったく手をつけていないということはないが、それでもギリギリになってあれもあった、これもだったという事態になることは免れない。
なかでも困るのは、日記。
書く方ももちろん大変だろうが、付き合う方も大変。
何日も遡って、あの日は何をしたっけ、この日はどこに行ったっけと聞かれて思い出すのは、思いの外しんどい労働だ。
だから題名だけでも毎日書いとけって言ったのに、ほんとにもう。
日記と言えば、この『ネオカル日記』だが、できるだけ毎日更新したいと思っている。
ただまあどうしても、なかなか毎日とはいかないのが現状なのだが、ひとつ欠かさず続けていることはある。
それがタイトルの『一日一話』だ。
確か二十歳の時くらいから始めたので、かれこれ数十年になるが、毎日ひとつ小話というかエピソードトークというか、考えるようにしている。
多くは出勤時や帰宅時の移動時間だが、それ以外にもすき間時間で考える。
この習慣があることで、いつも何かしらアンテナを張っていようとするので気づきも多くなるし、いい習慣だよなー、と自分では思っている。
だから、何かのタイミングでフッと話を振られて人前でしゃべることになっても、ネタの用意は出来ていて、それは心の余裕につながるよなー、とも思っている。
これからもぜひ続けていこうと思っているし、その話をできるだけここに投稿できるようにしたい。
私はそんな感じだが、長男のあっちゃんはあっちゃんで、最近ブログを始めた。
良かったら遊びに行ってあげてください(^.^)/~~~
【あさぶろぐ】https://asablo.amamin.jp/
Posted by 井田陽平 at
15:16
│Comments(1)
2024年08月14日
奈良の月

奄美もそうだと思うけれど、奈良も今年の夏は暑い。
なんか毎年、暑さのマックス値が更新されている感じで、35℃以上の猛暑日が何日もあって、今日もそうだ。
奄美から奈良に来て、気候ギャップ的に一番こたえたのは冬の寒さだが、夏の暑さも大概だ。
普通に考えれば、緯度が赤道に近いほうが気温は高いだろうし、実際、年平均気温とかを比べればそうなっているのだろう。
ただ、奈良には奄美とはまた違った暑さがある。盆地の暑さだ。
島だったら、暖められた陸上の空気が上昇して、暖まりにくい海上の空気が吹き込んでくる、いわゆる海風が吹くので、暑くなりすぎない。
これに対して盆地では、このような空気の循環を山地が遮ってしまうため、空気が流れず、気温が上がりやすい。
下手をすると、山の反対側で雨を降らせ、乾いて熱くなった風が吹き下ろしてくることになる。フェーン現象ってやつだ。
これが盆地の暑さのメカニズムだが、この“周りをぐるッと山に囲まれてる感”は暑さを倍増させる。
それと、たとえ海風が吹かなくても、あの青い綺麗な海が見られるのと見られないのとでは、感じる暑さに雲泥の差がある。
こっちに来てみて分かった。海があるのは思いの外、っていうか、超重要だ。
海なし県の奈良では無いものねだりなのだが、奈良にだって美しいものはある。
そのひとつが、月の美しさ。
明確な理由は分からないけれど、どこで見ても月は月なのだけれど、奈良の月はいい。なんかいい。
万葉集にも奈良の月はたくさん詠まれているが、その気持ち分かる、詠みたくなっちゃうよねーって思う。
先日は親戚のいる明日香村に行ってきたのだが、明日香村といえば、聖徳太子が政治を行い、大化の改新が起こり、日本最古の富本銭が見つかった場所だ。
そこの山に登る月も、また格別の味わいがあった。
この暑さを乗り切れば、秋から冬にかけて、中秋の名月や紅葉など、奈良が美しい季節を迎える。ぜひ奄美人にも見せたい美しさだ。
ただし、盆地の冬は超寒いけどね、これがまた。
Posted by 井田陽平 at
15:45
│Comments(0)
2024年08月13日
テレビがない

この話をすると、けっこう驚かれることが多いのだが、うちにはテレビがない。
テレビをあまり観なくなったきっかけは、東日本大震災。
あの頃はまだ千葉にいた。子どもは一番上の子だけで、当時2歳。
震災当日以降、来る日も来る日も被害状況や津波の映像が流れていて、それはとてもショッキングで、明るい話題などひとつもなかった。
そんなテレビを観続けていることが、大人も然ることながら、子どものPTSDにつながる危険性があるとの専門家の話を聞き、なるほど確かにそうだとテレビを消したのだ。
以来うちではテレビをあまり観なくなり、奄美で暮らした10年間は、テレビを設置することすらしなかった。
現在もそれは継続しており、そもそもテレビという機器を持ってもいない。
そもそもの話で言えば、私はかなりのテレビっ子だ。
というか、私たちの世代はみんなテレビと共に大きくなった世代と言っていいだろう。
朝起きてから夜眠るまで、食事の時もテレビはついていたし、実家には一部屋一台くらいの勢いでテレビが置いてあったけれど、それは当時の平均的な家庭だったと思う。
そんな私がテレビなしの生活をしている訳だが、これがまったくもって快適だ。
テレビはなくとも情報はスマホで十分だし、テレビを観たければPCでTverでも何でもある。
不自由は全く感じない。
良いところと言えば、家族の会話やコミュニケーションが多くなることだろうか。
他の家庭と比較できないのでたぶんの話だが、うちは会話が多いと思う。
家族全員がおしゃべりであることと、テレビがないことには正の相関関係があるだろう。
良いか悪いかは別として。
それとテレビを観ない分、よく本を読むかな。これは趣味嗜好の問題かも知れないけれど。
昔のように、テレビという共通言語を持たないとコミュニケーションが取れなかった時代ならいざ知らず、今はインターネットさえあれば全て事足りる。
なので、みなさんにもオススメしたい。テレビのない生活、いかがでしょう。
きっと、あっけない程すんなりと移行できるに違いない。
これぞ成熟社会におけるひとつ上のフェーズだと、自己満足することしきりなのである。
Posted by 井田陽平 at
16:00
│Comments(0)
2024年08月07日
流れを変えるプレー

いよいよ夏の甲子園が開幕した。
高校野球と言えば、やっぱり地元のチームを応援する人が多いのだろう。
私はと言えば、そうしていたのは中学生まで。
高校生になって以降は、そんな気はまったく起こらなくなった。
オリンピックなら競技を問わず、もちろんニッポンを応援するのだけれど。
では、どんなチームに肩入れするのかと言うと、母校だ。
私はサッカーが大好きだが、100%肩入れして応援するサッカーチームは2つしかない。
千葉県立八千代高校サッカー部と、日本代表。
高校ほどは思い入れがないものの、大学の駅伝とかラグビーとかはやっぱり、母校の早稲田を応援する。
それ以外は、どちらかを応援するというより、面白い試合が見られれば満足だ。
他のスポーツ、然り。
ただ、例外がある。奄美のチームを応援するのは、無条件だ。
こんなこと言ったら今住んでいる奈良の人に怒られるかも知れないが、奈良県代表と大島高校が甲子園で対戦したら、断然、大高に100%肩入れして応援する。
そんな大高が夏の甲子園にあと1歩まで迫った、現ソフトバンクの大野君がいた年の鹿児島県予選、ネットで観て奈良から家族で応援していた。
準決勝だったか準々決勝だったか、特に印象に残っているシーンがある。
確か8回、得点ビハインドでの攻撃中、バッターが外野フライに倒れた後だった。
3塁コーチャーズボックスにいた大高の選手が、突然コールドスプレーを持って、相手レフトの選手に駆け寄っていった。
実況のアナウンサーもにわかには状況が掴めずにいたが、レフトの選手はうずくまっている。
足がつったらしいのだ。
いやいやいや、3塁コーチャーが初めにそれに気づいて、コールドスプレーを持って、しかも負けている敵選手のところへ、真っ先に駆けつけるって、なかなか出来ないですよ。
私だったら気づいても、ざまあみろって思ってるだけですよ、たぶん。
負けてる相手だから悔しいし。しかも大詰め8回にアウトを取られた後。なかなか出来ないですよ。
私には、このプレーが試合の流れを変えたように見えた。
このあと大高は逆転し、見事に勝利を手に入れたのだ。
大高生ならではのファインプレー。なかなか真似できないファインプレー。
さてこの夏は、これに並ぶファインプレーが見られるだろうか。
試合も価値観もひっくり返してくれるような、とびきりのファインプレーが。
Posted by 井田陽平 at
21:40
│Comments(2)
2024年08月06日
ここまで出来たら教えてね

うちには今年、2人の受験生がいる。
受験生ではあるけれども、2人とも塾には行っていない。
長女は「うちで教わる方がいいから必要ない」と言って行かないし、長男はそもそも性分に合わないと思うから勧めていないし、本人もその気はないだろう。
結果、受験の天王山たるこの夏休み、家での時間、父はもっぱら夏期講習の講師を務めている。
子どもにこうやって個別に勉強を教えているときに、よく行きあたるのが、表題の「ここまで出来たら教えてね」問題だ。
問題集やプリントで、この問題まで解けたら教えてとか、このページまで終わったら丸付けねとか指示することはよくあるのだが、なぜかこれを守ってくれない子がいる。
ふと気が付くと、何題も何ページも先を進めていたりする。
ここまでだからねって、印をつけたり書き込んだり付箋を貼っておいたりしても、お構いなしだ。
こっちは、範囲を区切って理解度を確かめ、修正すべきところは修正し、新たに説明を加えるところは加えて進めていきたいのに、とっても困る。
そういう子たちの頭の中は、「目の前のこの課題をとにかく早く終わらせてしまいたい」ということなのだ。
経験上、ほとんどの子は、そう思っていると言っていい。
だから、時間を細切れにして都度都度修正される面倒を被るよりも、バーッと一気に終わらせてしまいたがる。
そうすると、どうなるか。
終わったあと一気に大量の丸付けをして、間違えた問題をズラーッと解説していくことになる。
こっちはそれも大変なのだが、肝心の本人はどうかというと、とにかく問題を解き終えた達成感で、半分以上気が抜けている。
解説が頭に入っていない。
さらに、理解度を確かめるために、新たに問題を用意しなければならなくなる。
都度都度修正していれば、最小限の労力で済んだものを。
ほんと、効率が悪い。
っていう話をうちの子たちにはして、そうはならないでおくれと言ってある。
お互い限りある時間と、入試というタイムリミットがある中での戦いだ。
あと半年かそこら、へのつっぱりはいらんですよ。
Posted by 井田陽平 at
15:17
│Comments(0)
2024年08月05日
速読王あっちゃん
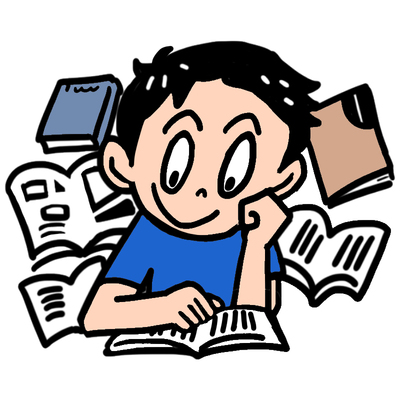
私の場合、だいたい週に1~2冊は小説を読む。
ジャンルは偏っていないつもりでいて、恋愛ものからミステリ、社会派と言われる作品まで何でも幅広く読む。
先日読み終わったのは、森絵都の『みかづき』。
昭和~平成の塾業界を舞台に、三世代にわたって奮闘を続ける家族の感動巨編だ。
自分が歩んできた塾業界という題材も然ることながら、時代設定も完璧にシンクロしている。
さらに、物語が展開する八千代台やら津田沼やら船橋といった地域は、奄美に移住するまで長いこと暮らしていた、思いっきりの地元だ。
主人公が経営する千葉進塾のモデルになったと思われる市進学院には、中学の頃に通っていた。
登場人物やストーリーはもちろんフィクションなのだが、学力テストやゆとり教育などの文部省の政策や、俗にいう津田沼戦争などの時代背景はリアル描写なので、かなり面白い社会派作品になっている。
で、うちの場合、私が読もうと思って買ったり借りたりしてきた本を目につくところに置いておくと、たいていは長男のあっちゃんが先に読んでしまう。
彼もジャンルを問わず何でも読むので、大人が読むような、子どもにはとっつきにくそうな本でも、サラリと読む。
小学生にしては難しい内容だったり、漢字が読めなかったり、表現が難しかったりもするはずなのだが、聞いてみるとよく理解して読破している。
しかも読むのがめっちゃ早い。
『みかづき』なんて467ページで厚さ4cmもある長編なのに、読破に半日もかからなかった。
立派な特技のひとつだと思う。
読書量と思考の深さは比例するとまで言えば言い過ぎかもしれないが、かなり重要なファクターだろう。
いい特技が身についてよかったね、あっちゃん。
Posted by 井田陽平 at
12:12
│Comments(0)
